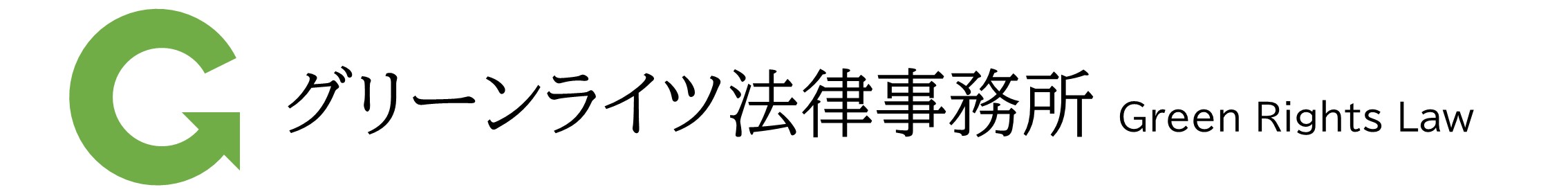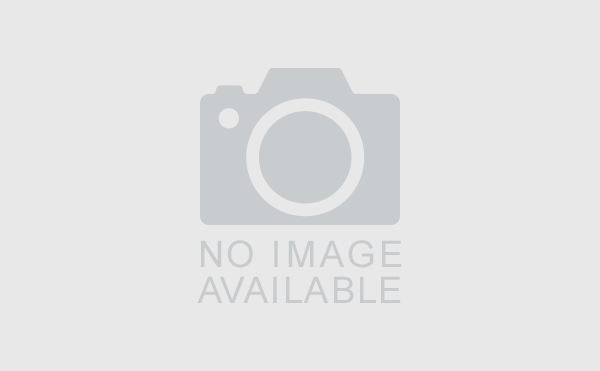北海道蘭越町における蒸気噴出事故について
2023年6月29日、北海道蘭越町において、三井石油開発株式会社(以下「三井石油開発」)が行う地熱発電調査事業の中で蒸気噴出事故が発生しました。
この事故により被害に遭われた方に、心よりお見舞い申し上げます。
また、現場で事故対応に当たっている方々の状況にも、当事者ではない者として、できる限りの想像をしないといけないと考えております。
それらを前提に、今回の事故について、以下記述します。
現場となったのは、北海道蘭越町の地熱発電採掘坑であり、
南西側の、温泉大湯沼につながる馬場川、
東側の、ニセコアンベツ川に流れ込むニセコアンベツ2号川の間に位置しています。
現地では、地熱発電に向けた調査が行われています。
事故現場(Google Map より)
事故原因について
三井石油開発によると、蒸気噴出のきっかけは、深度206~207mで亀裂に遭遇したことにあるようです。


出典:三井石油開発株式会社ウェブページ(7月10日開催の第2回住民説明会資料)
水質等の汚染について
本件事故による砒素汚染等について、報道がされているところです。
今回、グリーンライツ法律事務所では、本日(7/15)までの三井石油開発株式会社と蘭越町の公表データをとりまとめました。
本件の問題点
◆噴出水の処理能力がなかったこと
事故現場となった採掘抗では、噴出水を適切に処理する能力を備えておらず、
一部の噴出水を地層深くへ戻したほかは、敷地外へ流出させるしかなかったことが、
今回の汚染を発生させている根本的な原因の一つといえます。
◆流出の判断
三井石油開発は、7月2日、ニセコアンベツ2号川への白濁水流入を回避した結果、大湯沼側へ白濁水を流出させたとしています。
その結果、大湯沼側(観測地点O1からO3まで)の測定結果で、農業用水基準値である1リットルあたり0.05mgを超えるヒ素濃度が観測されています。
上記の処理能力のなさから、大湯沼側へ流出させる対応しかできなかったのかもしれません。
しかし、それによる地域住民や関係する方々の被害を最小限とするために、行政との協議や、住民に向けた継続的かつ正確な情報提供が必要な状況です。
◆対応の混乱
ところが、対応には混乱も見えています。
7月6日、三井石油開発は、以下のように大湯沼側への「放出」を決定し、実施したことを明らかにしています。
対応については、関係当局と協議しているとしていました。
7月3日に噴出現場直下に滞留している水溜まりにて採取した水質を分析したところ、砒素が11mg/Lと非常に高い値で検出されました。また、7月5日に掘削敷地内の濁水処理装置処理後に採取した水からは同じく15.9mg/Lと非常に高い値で検出され、これらを17時に確認しましたのでお知らせ致します。これらの水の大半は掘削敷地外の大湯沼方面へ放出し、一部はバキューム車にて取水して1km南南東の掘削済み井戸(約2500m)に注入しています。
水溜まりでの検出結果ですが、蒸気にも含まれている可能性があります。現在、関係当局にご連絡の上、対応を協議しております。
三井石油開発第14報 https://www.moeco.com/news/2023/07/-14.html
ところが、蘭越町は、協議を行った事実はないとして、抗議文を提出しました。
【令和5年7月7日第4報】
蘭越町第4報 https://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/administration/news/detail.html?news=528
湯里地域における蒸気の噴出に関する対応として、事業者が実施した河川の水質検査において砒素の含有が判明した以降、町は白濁処理水の適切な処理について事業者に要請を行ってまいりましたが、昨夜大湯沼方面に放出といった処理が事業者のホームページの第14報で公表されております。
また、水溜まりでの検出結果について、関係当局と協議を行っているとされたホームページの内容についても、町では協議を行った事実はありません。
以上のような事業者の対応に不信感が募り、本日開催された町議会議員協議会の冒頭、事業者に対し強く抗議を行ったほか、早急に北海道と協議し、白濁処理水の放出の停止と対策を講じるよう、要請しています。
さらに、三井石油開発の第2回住民説明会では、7月2日の時点で、すでに大湯沼側へ噴出水が流出していたことが明らかになっています。
7月2日(日)
三井石油開発第2回住民説明会資料p.4 https://www.moeco.com/news/pdf/2023_Setsumei.pdf
- ニセコアンベツ二号川への白濁水流入を回避した結果、大湯沼側への流出
◆モニタリングの遅れ
このような混乱の結果なのか、行われるべき大湯沼側の水質モニタリングについては、
本来は、遅くとも流出を把握した7月2日以降実施すべきところだったといえますが、
7月11日以降の数値しか公表されておらず、開始が遅れたものと考えられます。
このような事態をどこまで見込んで採掘調査に当たることができるか、
また、事後にいかに的確な対応を素早くとることができるかによって、地域への負荷は大きく変わります。
それを左右するのは、企業活動が地域の住民や環境の負荷の上に成り立っていることへの意識ではないかと考えています。
引き続き、事態の推移に注視したいと思います。